※この記事は広告を利用しています。

なんで自分ってこんな性格なんだろう?と思ったことはありませんか?
例えば、必要以上に他人の顔色を気にしてしまったり、友達と遊ぶのを楽しみにしていたのに、遊びから帰ってきたらなぜかどっと疲れて無気力状態になってしまう・・・
頑張っていたり、努力していても突然どうでもよくなりリセットしてしまいたくなる・・・
など、自分でも自分の気持ちや行動が理解できないことってたまにありますよね。
今回はそんな日常の何気ない行動の裏に隠された心理を解説していきます。
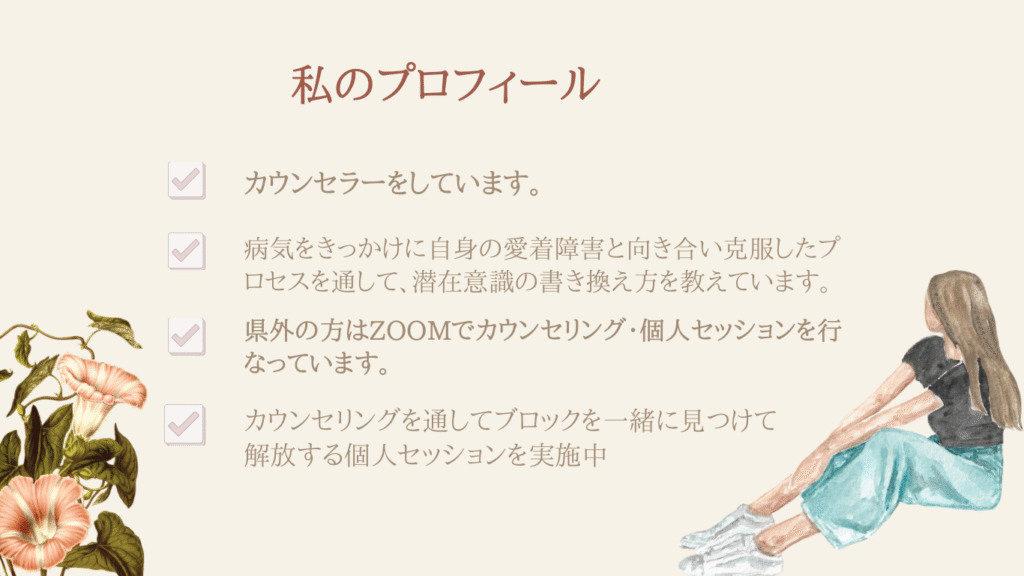
知ってると得する心理学
自分のことなのに時々なんでそんな風になってしまうのか・・・あるいはなんでそう感じてしまうのか
『自分の感情がめんどくさい』とか『なんで自分ってこうなんだろう』と自分の頭の中で考えていることが嫌になる瞬間ってありませんか?
そんな人の為になぜそうなってしまうのかを解説していきます。
また、人から理解してもらえない行動の裏にはこんな心理が隠れていますよ!という雑学を踏まえて解説していきます。
本音のを言うと涙が溢れる人
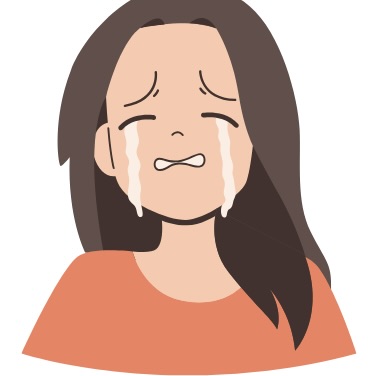
本音を口に出した瞬間に涙が出てしまう人は、今まで悲しい感情を抑えてきた人によくみられます。
それまで抑えていたストレスや不安から解放された証拠でもあります。
特に、今まで《強くいなければいけない》ような状況の中生きてきた人が多い。
『お姉ちゃんだからしっかりしなさい』『男なんだからこれぐらいで弱音を吐いてどうする』など、特に昭和の躾を受けて育った世代は、固定観念が強い親が多い傾向があります。
躾と題して子供の感情を押さえつけるような言い方をする親が多く、その家庭環境の中で育った人は、自分の本音を普段から抑えていることが多い傾向があります。
他にも、誰かが自分の境遇に共感してくれたり、痛みをわかってもらえた瞬間に涙が溢れてしまう人も同じで、心が癒された証拠でもあります。
急に何もかも嫌になって全てをリセットしてしまう人
日常的に我慢しながら仕事をしていたり、本当は好きじゃないのに頼まれたから仕方なく引き受けていることが日常に溢れていると、急に限界を迎えてしまい何もできなくなってしまうケースがあります。
『仕事に行かないと・・・』と頭では思っているのに体が動かないなんてことが起きたり
『この電話は取らないとまずい』と思っても手が伸びずにずっと見つめるだけで何もできない・・・
『私どうしたんだろう・・?』と焦っても、何も動く気にならない・・
とか、全てが急にどうでもよくなり『もういいや』と突然頑張っていたものをあっさり手放してしまうケースもあります。
そういう突然リセットしてしまう人は、普段から自分の気持ちを無視して限界まで頑張ってしまうことが多かったり、責任感が強すぎるあまり、なんでも自分で乗り越えようとした結果
日々のストレスが積み重なり、ついに限界まできた時に無気力という形でショートしている状態です。
そういう人は、意識的に休みをスケジュールの中に組み込むことが大切です。
何か予定を立てる前に休む時間や日時を先に決めてから仕事をするのがオススメです。
人は区切りがある方がやる気が続きやすいものです。
嫌な記憶を脳内で繰り返し考えてしまう人
嫌な出来事があると、そのことをなん度も繰り返し脳内で考えてしまう人は、自分責めをしてしまうことが癖になっていて、過去の失敗を手放すことが苦手な人が多い。
『あんなことしなければよかった・・・』『なんであんなこといったんだろう・・』といつまでも後悔してしまいがち・・
そういう人は真面目で完璧を自分に求めてしまう傾向がある。
また、不安を感じやすい人も、『また前のようになるかもしれない』と思いやすく、無意識に脳が警戒モードになってしまう。
過去の失敗をまた掘り返して『あの時もこうだったから』と、前回失敗してしまったことを持ち出して、ネガティブになってしまう。
これは自分をこれ以上傷つかないようにするための、脳の自己防衛本能でもある。
不安が強い時は、あの時に失敗してしまった原因を書き出してみて、客観的に失敗に終わった原因を探っていきましょう。
そして、今の自分はあの時と同じような失敗をしそうなのか?と自分に問いてみると、漠然とした不安が消えてくれます。
読書をすると眠くなる人
読書をしても眠気に襲われて中々読みきれずに途中で終わってしまう原因は、脳のワーキングメモリに負荷がかかりやすい傾向があります。
ワーキングメモリは読みながら意味を理解するので、前後の文を繋げて全体の流れを把握するという処理を同時にこなす働きをしているので思っている以上に脳には負担がかかっている。
すでに疲れが溜まっている状態や頭の中で考えごとがいっぱいの場合は、処理能力が低下しているため、どんなに本を読みたくても、《これ以上は無理》というサインとして眠気を誘発してしまいます。
また、勉強は仕事のためなど仕方なく読んでいる場合は、脳はそこに刺激や報酬を感じないので、ドーパミンの分泌を抑えてしまうので、退屈に感じてしまいやすく眠気を感じてしまいます。
どうしても読みたい本がある時は、起きたばかりで頭がリセットされた状態で読むか、本を読むことがリラックスできると思わせるために、おやつや自分の好きな飲み物とセットで楽しむようにすると、眠気を起こしにくくなります。
また、勉強のための場合は、この本から何を得たいのか最初に書いておくと、効率的に情報収集ができるようになります。
人の感情や表情を読みすぎる人
人の顔色を必要以上に気にしてしまう人は、精神的に疲れやすく、人といると気が休まらないことが多く、家に帰ってくるとぐったりしてしまうことが多い。
特に相手の些細な変化は『怒ってる?』『なんか気に触るようなことしたかな?』など嫌われたかもしれないと必要以上に不安になってしまう。
《嫌われたくない》という恐怖心が根底にあるので、自分の気持ちを置き去りにして過剰に周囲の人に合わせて《過剰適応》してしまう傾向がある。
そういう人は、高い共感力と観察力と繊細さを兼ね備えています。
そんな性質がネガティブに発動してしまうことが多い場合は、ポジティブに活用できる方法を意識的に練習すると強みに変わっていきます。
また、自分が必要以上に気にしいだということを理解した上で、人との距離感の保ち方を工夫するだけでもストレスは軽減できるようになります。
過剰になりすぎたストレスを解消する方法(自分が癒されると思う趣味)を日常の中に習慣として取り入れてみるのもオススメです。
人の悪口を言う人
悪口を言うのが多い人ほど、過去に自分が言われて傷ついたことを無意識に言ってしまっている。
これは投影反応という心の防衛反応で自分の中にある受け入れたくない感情や弱さを他人に重ねてみることで心を守ろうとする仕組みです。
例えば、『なんでこれぐらいもできないの?』といわれて傷ついた人は、その痛みを自覚する代わりに他人を《使えないやつだ》と思うことで自分の不安を外に押し出そうとします。
これは心の中にある未消化の感情が無意識に言葉として滲み出てしまっている状態である。
誰かを傷つける言葉にはその人自身がかつて傷ついた経験が隠されていることが少なくない。
また、本当は自分の欠点を自覚しているけど認めたくない場合も相手が自分と同じ性質を持っていることで投影が起こり苛立ってしまうこともあります。
人に悪口や不満に思うことがある場合は、自分にもそういう部分がないかを内省し気づくことができると他人に対してイライラしなくなります。
自分にとって当たり前にできること
周りの人から同じようなことに対してよく褒められることがある人は、本人からすると特別なことではないと感じるものは実はそこに才能や強みが隠れています。
人は誰しも他人と比べてしまう癖があり、自分に足りない部分に目を向けがちだか無理なくできることの中に自分だけの価値が隠れているのでそこを見逃さないようにしましょう。
人から褒められる部分はお世辞ではなく、本当にその人にとっては自分には出来ないことor羨ましいことだったりするので、素直に受け止めてそこを伸ばすようにすると自分の才能に気づくことができるようになります。
三日坊主の人
三日坊主で中々続けられない人は、早く理想の自分になりたくて、いきなり負荷のかかる行動を選びがちな傾向があります。
例えば、YouTubeやインスタなどで流れてきたダイエット方法で《3ヶ月でマイナス10キロ痩せました!》という動画を見て、その痩せた姿が羨ましくて早くそっち側にいこうとして、絶対に続かない方法でダイエットをし始めて結局挫折する傾向があります。
最初から気合いを入れすぎたり、力んでしまうと潜在意識から抵抗反応がでてしまうことで結局続けられない現実を引き寄せてしまいます。
理想が高すぎたり、完璧主義な傾向がある人ほど無理な目標設定をして自分に負荷や強いストレスをかけてしまう傾向があります。
そんな人は、スモールステップを意識して物事に取り組んでいきましょう。
運動習慣がない場合は、1日10分の軽めの運動から慣らしていくことが大切です。
そうして小さな成功体験を積み重ねることで習慣化できるようになっていき、一度習慣にすることができるとやる気に頼らずに普通にできるようになります。
同じ映画をなん度も繰り返しみてしまう人
同じ映画を好んでなん度も見てしまう人は、無意識のうちに自分の心を整えようとしていることが多い
お気に入りの映画には自分にとって心地よい感情や落ち着きを思い出させてくれるシーンが沢山詰まっているので、その映画をみることでホッとしたり安心感を持ってみることができます。
また、泣ける映画を敢えて見る理由も今の自分に必要な感情を自然に引き出してくれ、心のモヤモヤを浄化したくて好んで見てしまうのです。
アクション映画でもハラハラドキドキの緊張があっても展開を知っているので、安心して見ることができ心が無理なくその感情を味わえる状態になっているのでリラックスしてみることができる。
疲れている時や不安に思っている時ほど、心に負担をかけずに気持ちをリセットする助けになります。
その映画がなぜ見たくなるのか・どんな感情を味わいたいから見ているのかに意識してみると今自分が何を欲しているのかが見えてくるようになります。
サザエさん症候群になる人
サザエさん症候群(日曜日の夕方から夜にかけて、翌日の仕事や学校への憂鬱感や不安を感じる現象)
になりやすい人は、《1週間》という時間を一つの大きなタスクのように捉えていて、その始まりに心の準備をしたり、過去の出来事を思い出して(楽しくない記憶)なん度も脳内でリピートしてしまうことが原因で憂鬱になっていることが多い。
『またあんな会社に行かないといけないのか・・・』と今までの記憶を辿って憂鬱な気分を再現してしまうことで気分が悪くなっている場合があります。
未来のストレスを先取りして感じていて、心が過敏に反応している現象です。
こうしたストレスは、時間の感覚を捉え直すことで変えることができます。
例えば『またあの嫌な1週間の始まりか・・・』と考えずに、月曜日の朝はとりあえず頑張ってみよう!とか、仕事に行く前にちょっとした気分転換をしてみる(朝マックしたりカフェでコーヒー一杯飲んでから行ってみるなど)いつもの日常に背徳感を感じるような刺激を加えてみるのもオススメです。
または、大きい括りで考えずに午前中と午後のように小さく区切って考えることで心理的な負担は軽減できます。
お風呂やトイレにスマホを持って行く人
お風呂やトイレをしている時でもスマホを持って行く人は、何もしない時間に不安や落ち着きのなさを感じやすい傾向がある。
本来リラックスするはずの入浴時間にもSNSや動画などの情報を取り入れずにはいられないのは『静かな時間=退屈』と無意識に捉えている。
刺激が当たり前になってしまい逆に情報に触れない状態を不安に感じてしまうことでスマホが手放せなくなっています。
《暇だから何かを見るというより何かを見ていないと落ち着かない》という感覚が習慣化しているので無意識のうちにスマホに手が伸びてしまいます。
本来は心を休めるための《何もしない時間》がいつの間にか、埋めなければいけない時間に変わっている。
その習慣がさらに不安を作り出してしまう原因になっているので、スマホを手放す時間を意識的に作っていく必要があります。
人混みが苦手な人
人混みの中にいると疲れてしまう人や周囲の目が気になる人は、人の動きや視線など外部からの刺激に対して過敏に反応しやすい《感覚過敏》の傾向がある
他人からの視線を強く意識しやすく、公的自意識が高いために人が多い場所では立ち振る舞いや服装を過剰に気にしてしまう。
人が多い場所では常に気をはっている状態になりやすく、自律神経が緊張モードのままとなってしまうので、短時間でも強い疲労感を感じてしまう。
また、周囲に気を配りすぎるあまり相手のちょっとした表情や雰囲気の変化にも敏感に反応してしまう傾向がある。
ただ、このタイプはとても繊細な一面をもつ一方で空気を読む力や共感力の高さがあるため、人間関係において信頼されやすい資質があります。
頭の中で音楽が流れる人
頭の中で音楽が流れる人は、脳の中で「記憶の整理」が活発に行割われている可能性がある。
特に最近よく聞いている曲はまだ記憶として定着しておらず、無意識のうちに脳がその情報を再生しながら整理しようとしている。
この現象は作業中や睡眠前など注意が自分の内側に向きやすい状況で起こりやすく
これは脳が勝手に「記憶の処理モード」に入っているサインでもある。
音楽は感情とも深く結びついているため、再生される曲がその時の気分と密接に関係していることもある。
ストレスが多い人は、脳が不安や緊張を和らげるために過去に安心感を得た音楽を再生し気持ちを落ち着かせようとしている。
音楽でメジャーな曲を聴くより、マイナーな曲を聴く人は自分らしさを大切にする傾向があり、周りに合わせるより、自分の感覚で生きていたいという気持ちが強いタイプ。
このタイプは流行や評価に左右されることなく、たとえ少数派でも「本当にいいと思えるものを見つけたい」という探究心がある。
人と違うことをすることに不安を感じにくく「理解されないかもしれない」という孤独にもある程度耐えられる心の強さがある。
表面的な人気よりも作品の背景や作り手の想いなど、奥深い部分に価値を感じる傾向がある。
自分だけが見つけた《隠れた魅力》に特別な愛着をもちそこに自分だけの意味を見出すことができる。
辛い時ほど笑ってしまう人
本当は辛いのに笑ってごまかそうとする人は、心の中にある不安や悲しみを笑顔で隠そうとする癖がある。
本音を出すことで空気が重くなるのを避けたり周りに心配をかけたくないという思いが強い。
「つらい」と言えない環境で育ったり、自分の感情よりも他人を優先することが当たり前になっていることもある。
笑うことで気持ちを切り替えたり、その場の空気を保とうとするのは自分の感情よりも周囲との調和を優先してしまう傾向のあらわれでもある。
ただその分誰にも気づかれずに1人で苦しさを抱え込んでしまうことが多い。
本当につらい時は無理に笑顔を作らずに、信頼できる人にほんの一言でも打ち明けることで心の重さがふっと軽くなることもある。
写真に写った自分より鏡の方が可愛いと感じる
写真写りより鏡に写った自分の方が可愛く見えるのは、日頃から見慣れている《親しみのある顔》だからである。
私たちは普段鏡で見た左右反転の顔を繰り返し見ているため、その映像に自然と安心感や好感を抱きやすくなる。
一方で写真は他人から見た視点に近くいつも見ている鏡の顔と反転しているため無意識に「いつもと違う」と違和感を覚えやすくなる。
また、鏡をみるときは無意識のうちに目を大きくしたり広角をあげたりして、自分が一番よく見える表情や角度に調整していることが多い。
それと比べて写真はふとした瞬間を切り取ったもので、表情が硬かったりタイミングが悪かったりするとそのまま印象が決まってしまう。
その結果、鏡の自分の方が『可愛く見える』と感じやすくなる。
写真の自分に違和感がある場合は「慣れ」と「見せ方」の差によるものが多い。
まとめ
今回は、知ってて得する心理の雑学を解説してきました。
自分がいつもとっている行動の裏の心理を知ることで生きやすくなったり、自分にとってよくない習慣は改めることを意識できるようになります。
また、「なるほど!そういうことだったのか!」という体験は脳にいい刺激を与えます。
自分の性質の心理を知ることで、気づきを得られ無駄にストレスを溜め込むことがなくなることもあります。
また、友人にそういう人がいる場合は教えてあげるのもオススメです!



















