※この記事は広告を利用しています。

――「今ここ」に還るための心の整え方――
人はみんな、不安と一緒に生きている。
どんなに穏やかに見える人でも、どんなに成功している人でも、心の奥には小さな不安が潜んでいる。
それは決して悪いことではなく、「よりよく生きたい」という生命の感覚そのものだ。
ただ、現代の人たちは、いつも過去か未来に対して意識が向きすぎていて、《今》を生きていない
不安を作り出してしまうのは、未来や過去に意識が飛んでいる状態だから。
“まだ起きていない出来事”を、あたかも現実のように感じ、今の自分の生活や地位に満足できない。
だから、“まだ足りない何か”を探し続けてしまう。
何かを付け足したら「うまくいくはず」と漠然と思い込んでいる。
だからこそ、不安と向き合う第一歩は、「不安をなくそうとしないこと」、不安をなくすより、その出どころをキャッチする力を養う方がずっと生きやすくなります。
今回の記事は、タイプ別の「不安」と対処法を解説していきます。
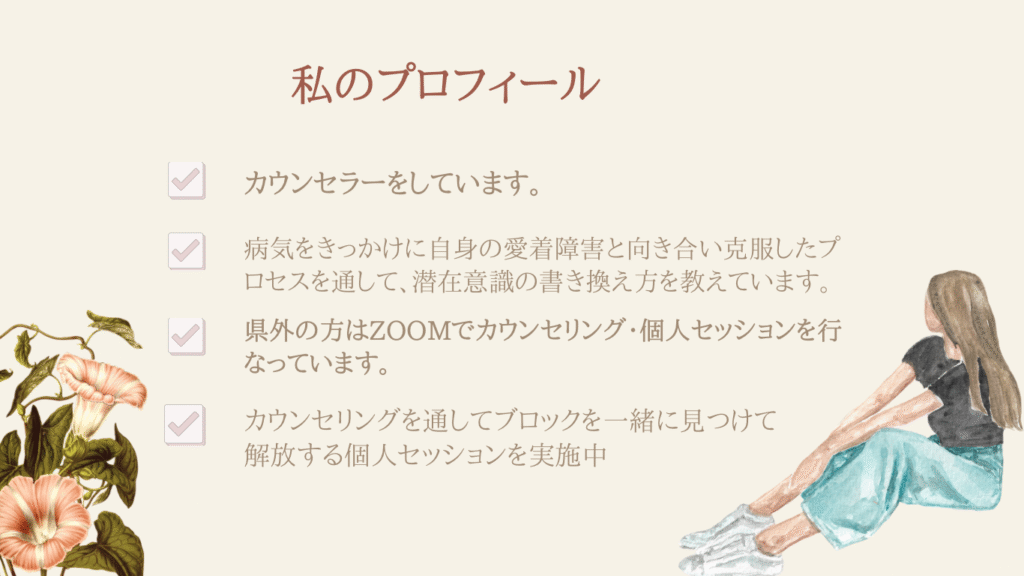
1.お金の不安 ――「なくなるかもしれない」という幻想
お金の不安は、ただ「生活できるか」だけの話じゃない。
もっと奥にあるのは、**“選択肢がなくなることへの恐怖”**だと思う。
欲しいものを選ぶとき、時間の使い方を決めるとき、人との距離を測るとき
どこかで “お金”という見えない軸が、すべてを仕切っている。
好きな仕事より、稼げる仕事を選ぶ。
休みたいのに働く、働かないとお金がないから仕方なく仕事をする。
愛よりも安定を優先して関係を続ける。
本当は離婚したいのに〈家のローン・子供の学費・生活費〉一人でできる自信も余裕もないから現実的に厳しいからで離婚ができない。
または、その逆で、結婚したいけど「お金がない」
奨学金の返済で毎月やりくりするだけでも大変で、将来のことを考える余裕もない。
ましてや結婚して子供が産まれれば余計にキツくなる。
今の状態では、自分のやりたいことすらできない。
そんな状態になっている人もいると思います。
「生きるため」が、いつの間にか「お金に支配される理由」になっていく。
お金の不安とは、**“生きる選択権を奪われる恐怖”**のこと。
その恐怖には、見栄やプライド、そして世間体が絡みつく
「普通の暮らしができない自分」にはなりたくない。
子供にお金で苦労させたくない。
「周りより下に見られる自分」も受け入れたくない。
今の生活水準から落としたくない。
そう思うほどに、人は自由を失っていく。
本当は、誰もが気づいていないだけで、“不安”という言葉の奥には、**「自分の人生を自分で選べないかもしれない」**という恐怖がある
そして、死の恐怖とも直結してしまう。
返済ができない恐怖。
最速のハガキに怯える毎日。
毎日食べるものに困る。
大切な人やペットを守れない恐怖との戦いでもあります。
その恐怖から逃れるために、やりたくない仕事でもやらないといけないという負のループに入ってしまいやすいのがお金の悩みでもあります。
2.仕事の不安 ――「この先もこの道でいいのか?」という迷い
仕事の不安は、やりたいことがわからない曖昧さから生まれるんじゃない。
心から納得できていないまま、日々をこなしていることから生まれる。
好きでも嫌いでもなく、ただ生活のために働く。
でもそこには情熱がない。
「これが自分の道だ」と思える確信もないまま、言われた業務だけを淡々とこなしていく
命を燃やして取り組んでいる感覚がないから、どこか“やらされている”ような気持ちになる。
本気で打ち込める仕事なら、大変でも、疲れても、どこかに納得感や充実感がある。
でも、その手ごたえがないまま与えられた仕事をやっているから、心の奥に“このままでいいのか”というモヤモヤがたまり、それが不安となって顔を出す。
だからといって自分がやりたいことってなんだろう?
やりたいことがあってもそれをお金に変えていく力がない。自信がない。知識がない
好きなもので食べていくなんてできるはずもないけど、今のままでいいかと言われれば、答えは「NO」に近い。
だからって何か行動することもできないまま時間だけが過ぎていってしまう。
3.将来への漠然とした不安 ――「このままでいいのか」
仕事のこと、お金のこと、家族、老後、健康、子どもの未来、自分の夢——
全部が同時に絡んでくるような複雑で漠然とした不安を持つ方が多いのではないでしょうか。
だから一つを考え始めると、他の問題も同時に顔を出す。
たとえば、仕事、この先どこまで続けられるのか、定年した後に何が残るのか?
キャリアを積んでも、年齢や環境が変わればまた一からやり直しになるかもしれない。
「この働き方のままで、十年後も自分は納得していられるのか?」
そう思う瞬間がある。それにお金、老後の貯金、子どもの教育費、家のローン。
数字を見つめるたびに、「これで足りるのか」「何が起きてもやっていけるのか」と計算が止まらなくなる。
家族との関係も同じ、夫婦としてどう生きていくのか(このままこの人と一緒にいたいのか)
子どもが成長したら、自分の人生をどう広げるのか。
どのテーマも、それだけで一つの人生を飲み込むくらいの重さがある。
この不安のやっかいなところは、何か一つを動かすと、他が揺れる構造になっていることだ。
仕事を変えれば収入が変わり、生活も変わる。家庭を優先すれば、自分の時間が減る。
自由を選べば安定を失い、安定を選べばどこかで息が詰まる。
だから、人はどれも“決めきれない”まま立ち止まる、「このままでいいわけじゃないけど、何を変えたら納得いくのかが分からない」いや本当はビジョンがあるけど、今の生活を手放す勇気はないから悩んでしまう人もいると思う。
それが、将来の不安の正体になっているのかもしれない。
そしてもう一つ、この不安が消えない理由がある、それは、多くの人が心のどこかで“正解”を探している。
「これを選べば、もう悩まなくて済む」という答えやこの道を選べば「幸せになれるはず」と・・・
でも、そんな答えはどこにもない。
人生には、確実なルートなんて存在しない。
だからこそ、「これを選べば正しい」「これを選べば失敗しない」という幻想を手放せない限り、不安はなくならない。
将来の不安とは、**「不確実さを受け入れられない心の反応」**でもある。
みんな未来を怖がっているんじゃない、未来が“決まっていない”ことを怖がっている。
だから何かを決めようと焦る。
でも、決めれば決めたで、「本当にこれでよかったのか」と迷う。
人はいつも、“確実な明日”を探してしまう。でも、そんなものあるはずない
それを頭では分かっているのに、心が受け入れられない。
――それが、将来の不安の一番の正体だと思う。
4.人間関係の不安 ――
人間関係の不安って、「嫌われたくない」よりも、“自分を出せないまま関わり続けている”ことから生まれる。
職場でも、友人関係でも、コミュニティーでも、人と関わるときに本音より空気を読む。
「本当はこうしたい」と思っても、その場の調和を壊すのが怖くて動けない。
自分の意見があっても、多数派に合わせて“それでいいよ”と笑ってしまう。
誰も悪くないのに、家に帰ると胸の奥に「これでよかったのかな」が残る。
そうやって、自分を少しずつ小さくしていくうちに、心が納得していないことに気づく。
「このコミュニティに本当に居場所があるのか」
「ここにいる意味は何なのか」
そんな問いが、夜の静けさの中でふと浮かんでくる。
でもすぐに、「でも仕事だから」「でも子どものためだから」
「でも今さら抜けられないし」って、理由を並べて自分をなだめる。
そうして無理に自分を納得させようとするたびに、心の奥の不安は少しずつ膨らんでいく。
それは「嫌われるかもしれない」という恐れじゃなくて、“本当の自分を置き去りにしている”という違和感だ。
人間関係の不安とは、“他人とうまくやれていない”不安ではなく、“自分とうまくやれていない”不安でもある。
💠 不安の正体は心の中の二人の自分《インナーチャイルドとマザー》の関係

不安を感じているとき、心の中では二人の自分が動いています。
ひとりは、怖がって泣いている小さな子ども。
それが“インナーチャイルド”もうひとりは、その子を見守る“インナーマザー”
不安の正体は、チャイルドが「怖いよ」「どうしよう」と声をあげている時です。
インナーチャイルドは幼い頃に傷ついた自分なので、またあの痛みを味わうかもしれないと思うと、《不安や怒り焦燥感》という感情を使って私たちを悩ませたりします。
でも、それは悪いことでなく、《あなたを危険から守るためのブロック》でもあるのです。
その幼い子供が怖くて泣いている、そこにもう一人登場するのがインナーマザー。
多くの人の心の中では、その声を聞いたマザーが、「泣かないで」「しっかりして」「情けないよ」「もっとやれるでしょ」「こんなこともできないの」
と叱ってしまう。
それは、かつて自分が母親からそう言われてきた記憶が、インナーマザーの口を通して再現されているだけ。
だから、不安が消えないのは“感じすぎているから”ではなく、**“安心させてあげられない関わり方をしているから”**
**“大人の自分(インナーマザー)が、心の中の子ども(インナーチャイルド)に対して安心を与えられていない”**ってこと。
🔹 インナーチャイルド(子ども)
…不安や寂しさ、怖さを感じて「助けて」「どうしたらいいの?」と泣いている部分。
🔹 インナーマザー(母性・大人の自分)
…その子の声を聞き、安心させたり抱きしめたりする役目の部分。
ところが、
多くの人は「不安を感じる自分」をダメだと思ってしまう。
「こんなことで不安になるなんて弱い」
「もっと頑張らなきゃ」
――この“否定”をしているのが、インナーマザー。
つまり、不安を感じているチャイルドに対して、マザー(大人の自分)が安心を与えるどころか叱っている状態。
「泣かないで」「しっかりして」「情けないよ」って、まるで昔の親の口調をそのまま再現してしまってる。
だから「安心させてあげられない関わり方」というのは、外の誰かじゃなくて、自分の中の“大人の自分”が、“小さな自分”に対してしている関わり方なんだ。
①お金の不安 ――「なくなったらどうしよう」
インナーチャイルド:
「もしお金がなくなったら、どうやって生きていけばいいの?
ちゃんと生きていける?
誰かに迷惑かけちゃうかも…怖いよ。」
インナーマザー(未熟な反応):
「そんなこと考えてないで働きなさい!考えても仕方ないでしょ!」
→ チャイルドは、“私は怖がっちゃいけないんだ”と感じて黙り込む。
インナーマザー(成熟した関わり):
「怖いよね。ちゃんと生きていけるか不安なんだね。
でも大丈夫。今までもなんとかなってきたし、これからも一緒に考えていこう。
お金が減る=命がなくなるじゃないからね。」
→ チャイルドは、“あ、わかってもらえた”と安心して力が抜けて、本当にやりたいことや本音が素直に言えるようになる。
②仕事の不安 ――「このままでいいの?」
インナーチャイルド:
「仕事、嫌じゃないけど、なんか違う気がする。
でも辞めたらどうなるんだろう。私、何がしたいんだろう…。」
インナーマザー(未熟な反応):
「贅沢言わないの。どこ行っても同じよ。今のままで我慢しなさい。」「次の転職がうまくいかなったらまた転職する気?」「世間体がよくないからやめなさい」「せっかく就職できたのに無駄にするの?」
→ チャイルドは、“やっぱり私の違和感は間違いなんだ”と思って気持ちを閉じる。
インナーマザー(成熟した関わり):
「“なんか違う”っていう感覚、ちゃんと大事だよ。
すぐに答えは出さなくていいけど、どんな働き方ならワクワクできるか、一緒に探していこうか」
→ チャイルドは、“この気持ちは無駄じゃないんだ”と感じて希望が戻る。
③将来の不安 ――「この先どうなるの?」
インナーチャイルド:
「このまま歳をとって、もし一人になったらどうしよう。仕事もなくなって、お金も足りなくなったら…。」
インナーマザー(未熟な反応):
「そんな先のこと考えたって無駄!今をちゃんとしなさい!」「そんなこと考えて何になるの?今目の前のことをしっかりと片付けなさい」
→ チャイルドは、“先を考えちゃいけないんだ”と抑えつけられ、不安が形を変えてまた湧いてくる。
インナーマザー(成熟した関わり):
「未来のこと、怖いよね。
“どうなるか分からない”って本当に不安だと思う。
どんなことが不安なのか一緒に考えてみようか」など、その気持ちに寄り添ってただ聞いてあげるだけで、不安に感じていた気持ちも和らいでいきます。
→ チャイルドは、“未知の未来も、ひとりじゃないんだ”と安心する。
④人間関係の不安 ――「嫌われたくない」「言えない」
インナーチャイルド:
「また本音を言えなかった。
言ったら嫌われるかもって思った。
私、どうしていつも我慢しちゃうんだろう…。」
インナーマザー(未熟な反応):
「空気読めてるからいいじゃない。
波風立てないのが大人なの。
自分の気持ちばっかり言ってたら人間関係うまくいかないわよ。」
「自分の気持ちを言って浮くよりマシ」
→ チャイルドは、“私の本音って迷惑なんだ”と感じて自分を責める。
インナーマザー(成熟した関わり):
「また我慢しちゃったね。
でも、その優しさもちゃんとわかってるよ。
本音を言うのが怖いのは、
“拒まれるのが痛い”って知ってるからなんだよね。
今度は少しずつ、“自分を守るために本音を言う練習”をしていこう。」
→ チャイルドは、“私が怖いのは悪いことじゃない”と安心し、
少しずつ自分を表現する力が戻ってくる。
私の中のインナーマザー(体験談)
私はいつも母親に否定されて育ってきました。
隣近所に住んでいる同級生と比べて家事や手伝いができない子として蔑まれて、家庭訪問の際には、先生に何もできない「どうしようもない子」と言われて下げられることばかりを言われていて。
毎回恥をかくような体験をしていました。
そして、先生も別にかばうような発言もなく、「算数が少し苦手で、でも体育はとっても楽しそうにやっていますよ」
とフォローになっていない言い方ばかり・・・だから教師がずっと嫌いでした。
そのせいもあってか、私は今だに子供の三者面談などが嫌いでどうしようもないくらいイライラしてしまいます。
夏休みになると家の掃除をしないと怒られ、冬になるとキビ刈りを手伝わされて子供時代を過ごしました。
唯一自分のしたいことを許されたのはバレーだけ
基本私のやりたいこと、してることに無関心で自分がやって欲しいことだけ厳しくしつけられました。
幼少期からずっと言われ続けてたのが、「家の中でやることは外でもやる」そして、家事や料理ができないと女じゃないみたいな言い方をされて育ったため、小学生の頃から料理は作っていました。
そのおかげで料理は人並み以上に得意になったものの
仕事に就くと、このインナーマザーが強烈になっていきました。
16の時から仕事を他県でしはじめて、その時も「偉いねー」と褒められても、あまりピンとこず
仕事がある程度できるようになっても、「こんなんじゃダメだ。あの人みたいにならないと」とベテランのできる人と自分を比べては自己否定をし続けていました。
可愛い子をみると劣等感を感じ「私もあの子みたいに可愛くなりたい」と外見だけに憧れ続けて、濃い化粧をして「こうじゃなきゃ愛されない」「あの子みたいに可愛くなれないとモテない」と思い込んでいました。
また、洋服選びも女性としてではなく、性の対象としてみられるためのファッションを好んだり、自分が好きか、よりも相手に見て欲しいが勝っていて、着心地の悪いものでも我慢して着たりしていました。
33歳の時に病気になるまで私はずっと、自分はダメな人間で人よりも劣っていると感じながら生きてきました。
頼ることが苦手で全部を自分で何とかしようとしてしまう。
でも、病気で働けなくなった時に、何もできない・身動き取れない状態になって初めて他人に甘えるということを自分に許可できました。
そして、コロナの影響で面会ができない状態だったので、そのことにもとても心を救われたんです。
子供もいて、自分の時間を取れなかった私は病気になってd初めて、「甘える」こと「全部を委ねる」ことができて、本当に嬉しかったんです。
赤の他人だからこそ、縋ることができたのかもしれません。
また親が病室に来ないということも何よりも嬉しくて、「気を張らないで済む」という安堵感を味わえたのを覚えています。
親はいつも、私の家に来るたびに「部屋が汚い。掃除しなさい」が口癖でいつも粗探しばかりで、親がくると「またなんか言われる」と身構えてしまう自分がいました。
それだけ心に安全基地がなく、今までずっと自分を否定しながら努力してたんだなと気づきました。
インナーマザーが厳しすぎるとインナーチャイルドは萎縮する
インナーマザーが厳しすぎると、インナーチャイルドは“感じること”そのものを怖がるようになる。
たとえば本当は「怖い」「寂しい」「悔しい」って感じていいはずなのに、マザーがいつもその感情に対して――
「早くやりなさい」「宿題はまだなの?」
「泣いたって何も変わらないでしょ」「あんたが悪いんでしょ」
「感情的になるのはみっともない」「泣いてないでもっとしっかりしなさい」
って言葉をかけ続けると、チャイルドは次第に「感じる=怒られること」だと学習してしまう。
そうなると、心の中でこんな反応が起きる👇
🌙 感情を感じた瞬間に、理性がそれを押し殺す。
泣きたくなっても「我慢しなきゃ」と抑える。
怒りを感じても「そんな自分は嫌われる」と飲み込む。
結果、チャイルドは「感じても受け止めてもらえない」から、だんだん心の奥に引きこもっていく。
この状態が長く続くと、外から見ると
“しっかりしてる人”“落ち着いてる人”に見えるけど、内側ではずっと孤独。
感情がフリーズして、嬉しい・悲しい・楽しいの区別がつきにくくなったり、「何が好きかわからない」っていう空虚感が出てくる。
そして最終的に、「人に頼れない」「弱音を吐けない」「完璧じゃないと愛されない」
という信念を持つようになる。
つまり、インナーマザーが厳しすぎるというのは、“感情の安全基地”がないということ。
心の中に、安心して泣ける場所が存在しない。
だからこそ、癒しの第一歩は、マザーがチャイルドに向かってこう言い直すこと。
不安をなくそうと努力するよりインナーマザーを育て直す

🌷インナーマザーは、“母親の声”を受け継いでいる
私たちの中にあるインナーマザー(大人の自分)は、実は「母親から受け取った関わり方の記憶」でできている。
あなたの母親は、あなたにどんな態度で接していましたか?
泣いたときに何を言われたか。
失敗したとき、怒られたか、励まされたか。
――その一つひとつが、今の自分の“心の中の母親像”を形づくっています。
不安を感じるとき、心の中で響いているのはたいてい昔の“母の声”だったりします。
母親がなきいま、自分の中に自分が見てきた、聞いてきた母親を作り上げ、そのインナーマザーがあなたの思考の元になっているのです。
それは、母親が悪いという話じゃない。
母親もまた、自分の母親(=あなただから見た祖母)から同じような言葉を受け取ってきたから、
世代を超えて受け継がれた“我慢の連鎖”が、そのままインナーマザーに刻まれているだけなのです。
だから不安を感じるとき、自分の中のマザーがつい厳しくなるのは当然のこと。
でも、今の私たちはもう“大人”になっているので、母親のように自分を躾けるような言葉をかけなくてもいいのです。
そう、不安と向き合うにはインナーマザーを育て直すのです。
ここからは、自分の中のマザーを「恐れで守る母」から「理解で包む母」へ
育て直しの方法を解説していきます。
たとえば、母親に言って欲しかった言葉を、今の自分が自分に言ってあげる。
「泣いていいよ」「よく頑張ったね」「すごいじゃん」「えらいね」「怖かったね」「もう頑張らなくていいよ」
こんな風に、本当は欲しかった愛情表現や言葉を今の自分が自分のために作っていくのです。
不安を癒すというのは、インナーチャイルドだけでなく、母親から受け継いだ“愛し方の癖”を
自分の世代で変えていくこと。
それが、インナーマザーを育て直すということです。
私が「こんな母親の元で育ってみたかったな」と思う理想の母親像が思い浮かぶ人はリストにして書いてみてください。
そして、悩んだ時に実際に言われたい言葉を自分にかけてあげる練習を紙とペンを使って練習するのです。
これをやっていくと、次第にセルフトークの質が変わっていって、考え方も変わっていくようにないます。
自分自身に対して批判的な言葉が多かった人は、自分の弱さを受け入れられるようになっていきます。

私もインナーチャイルドワークをする時に同時に、インナーマザーも育て直すことをしていたので、今では批判的な自分自身はいなくなり、不安になっても心がモヤモヤしてもその感情としっかりと向き合うことができるようになり、ストレスが昔の10分の1に減りました。
ここからは、不安で夜も寝れない時にやるといい対処法を紹介していきます。
インナーチャイルドワークと同時にやると気持ちが楽になっていきます。
🌫️不安の出所をキャッチする

それは、ただ「不安だ」と思うだけでなく、
- その不安がどんな思考から生まれたのか?
- そのとき身体のどこに違和感があるのか?
- その感覚は過去のどんな記憶や状況とつながっているのか?
を丁寧に観察すること。
たとえば、
「仕事がうまくいかない不安」があるとき、
それは「評価されないかもしれない」「見捨てられるかもしれない」という根底の恐れがあるかもしれない。
そしてその瞬間、胸がぎゅっと締めつけられるような感覚があるかもしれない。
その身体感覚を無視せず、「あ、今ここに痛みがある」と認識することが、第一歩。
🧠ロジカルに考える × 🫀身体感覚を観察する
ロジカルに考える
- その不安は、何に対しての予測か?
- その予測は、事実に基づいているか?それとも過去の記憶か?
- その記憶は、今の自分にとって本当に有効か?
実際にノートとペンを用意して、何を怖いと思っているのか・あなたが感じている最悪の事態とはどんな状態になっているのかを、実際に紙に書いて可視化して、恐れと向き合ってみる。
そうすることで漠然とした不安や、グルグル思考の正体が掴めるようになってきます。
最悪の状態が起きた時に今の自分でできる対処法は何があるのか。
もし、全てを失った時にどう立て直すことができるのか?をシュミレーションしておくと不安が嘘みたいに消えることもあります。
身体感覚を観察する
- 不安を感じた瞬間、どこが重くなる?
- 呼吸は浅くなっている?手足は冷えている?
- その感覚を、ジャッジせずにただ見つめる
この2つを同時に行うことで、不安を「感じる」だけでなく「理解する」ことができるようになる。
体のどこかに違和感や不快感を感じるなら、深呼吸しながらそこをそっとさすって「大丈夫だよ。私がついてる」と違和感や不快感がなくなるまで続けてみましょう。
イメージングが得意な方は、自分の体の周りをゴールドの繭が覆うようなイメージをしてみるのもオススメです。
🪷実践:不安をキャッチするための3ステップ
- 不安を感じた瞬間に立ち止まる
「今、私は不安を感じている」と言葉にする。その感情から逃げないことが大事。
ここで、別の何かをして気を紛らわせても、どうせまた同じ思考が頭をグルグルしてしまう - 身体に問いかける
「どこが重い?」「どこがざわついてる?」と内側に意識を向ける。
手のひら、胸、喉、みぞおち、背中――どこかに“サイン”があるはず。
モヤモヤしてるのか、ザワザワしているのか、何かの痛みを感じるのか、体の反応に意識を向けてみる - 思考を整理する
「この不安は何から来てる?」「なんでそう思ってしまう?」「どんな状態になることを恐れているの?」と自分に質問してみる
最悪のシナリオを紙に書いてみることで、実際に視覚化した瞬間にその思いは幻想だということがわかると思います。
🌌不安は「魂の声」でもある
不安はただのノイズではなく、魂が何かを訴えているサインでもあります。
「このままでいいの?」という問いかけは、魂が変化を求めている証かもしれません。
人は、生まれてくる前に自分がやりたいことを決めてくるという説がありますが、もしそうなら、違和感の正体は、本来の目的からズレているから不安になり、「このままでいいの?」という問いが生まれているのかもしれません。
だからこそ、無視せず、逸らさず、対話することが本来の自分の進みたい道へ戻るための鍵になっていくと思います。
不安を感じるのは「今」に生きていないから
不安は、未来や過去に意識が飛んでいるときに生まれます。
「起きていないこと」を想像し、「過ぎたこと」を何度も再生して、頭の中で仮想の現実を作ってしまう。
でも本当の現実は、いつも“今ここ”にしかない。
呼吸している。
心臓が動いている。
空があって、光がある。
その事実を感じられる瞬間に、不安は静かに小さくなる。
不安を消すことはできなくても、“今ここ”を感じることで、不安に飲み込まれない自分には戻れる。
そしてその繰り返しの中で、人は少しずつ「安心という筋肉」を育てていけるのかもしれません。
まとめ ―― 不安は「自分と繋がる入口」
不安とは、欠けている自分を責めるためのものではなく、「本当の自分を思い出して」と教えてくれるメッセージだ。
お金の不安には「受け取ることへの不信感」、仕事の不安には「正解を探す癖」、将来の不安には「心と現実のズレ」、人間関係の不安には「自分との断絶」が隠れている。
そのどれもが、“いまの自分”を生きていないときに現れる。
不安を悪者にせず、「戻る場所を教えてくれてありがとう」と言ってみてほしい。
それだけで、心の波が少しずつ静まっていく。
不安は、消すものじゃない。
生きてる証。
そして、“今ここ”に帰るための道しるべです。



















